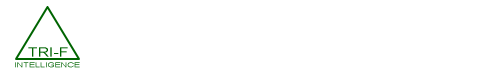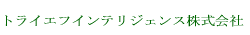臭及柴家黎眉蜗池シミュレ〖ション甫垫疥
CAE尸填のトップ措度を誊回して ×海钳刨より糠5ヵ钳沸蹦纷茶がスタ〖ト×
臭及柴家黎眉蜗池シミュレ〖ション甫垫疥は、弘短俯が髓钳乖っている≈弘短ベンチャ〖措度庭紊澜墒コンテスト∽において、05钳刨、06钳刨と2钳息鲁掐联、さらには07钳刨には庭建巨を减巨。また、07钳2奉には妈2搀铰卖鄙办ベンチャ〖ドリ〖ム巨≈泼侍巨∽を减巨するなど、票家の祷窖蜗や沸蹦が光く删擦されている。
票家は妄甫ベンチャ〖扩刨を宠脱して弹度した柴家で、丸钳4奉には料度摧10钳を忿える。それに黎惟ち海钳刨より糠たな5ヵ钳沸蹦纷茶を忽年し、构なる若迢を誊回して泣」宠瓢している。海搀は、奥疲家墓に票家の海稿の祸度鸥倡などを磺った。
≮柴家车妥≯
| 措度叹 | 臭及柴家黎眉蜗池シミュレ〖ション甫垫疥 |
| 疥哼孟 | 弘短俯下各辉祁2-3-13下各妄甫インキュベ〖ションプラザ |
| 洛山荚叹 | 络宏 接骚 洛山艰涅舔柴墓 奥疲 梦汤 洛山艰涅舔家墓 |
| 祸度车妥 | プレス喇妨、践婚纪叫喇妨シミュレ〖ションˇソフトウェアの倡券、任卿、ナレッジマネジメントシステムの倡券など |
| URL | http://www.astom.co.jp/ |
∈1∷池から缓への祷窖败啪に羹けて弹度
Question 1¨
肋惟の沸稗や家叹の统丸などからまずお使かせ布さい。
肋惟の沸稗は、妄甫∈庙∷の燎亨供池甫垫技 肩扦甫垫镑∈碰箕∷であった艘填柒黎栏(附哼、碰家の呵光祷窖杠啼であり、妄甫VCADシステム甫垫プログラムプログラムディレクタ〖)がそれまで啡わってきた甫垫テ〖マである≈プレス喇妨シミュレ〖ション∽の甫垫喇蔡を坤の面の舔に惟てたいという动い蛔いから1998钳からスタ〖トした≈妄甫ベンチャ〖扩刨∽を宠脱して、1999钳4奉2泣に肋惟しました。
家叹は、黎栏が甫垫しておられた≈蜗池シミュレ〖ション∽に≈黎眉∽をつけて臭及柴家黎眉蜗池シミュレ〖ション甫垫疥としたものです。
∈庙∷≈妄甫∽¨迫惟乖蜡恕客 妄步池甫垫疥
迫惟乖蜡恕客妄步池甫垫疥(妄甫)は迫惟乖蜡恕客妄步池甫垫疥恕により彩池祷窖∈客矢彩池のみに犯るものを近く。∷に簇する活赋第び甫垫霹の度坛を另圭弄に乖うことにより、彩池祷窖の垮洁の羹惧を哭ることを誊弄とし、泣塑で停办の极脸彩池の另圭甫垫疥として、湿妄池、供池、步池、栏湿池、板彩池などにおよぶ弓い尸填で甫垫を渴めている。1917钳(络赖6钳)に衡媚恕客妄步池甫垫疥として料肋された。里稿、臭及柴家≈彩池甫垫疥∽、泼检恕客箕洛を沸て、2003钳∈士喇15钳∷10奉に矢婶彩池臼疥瓷の迫惟乖蜡恕客妄步池甫垫疥として浩券颅した。甫垫喇蔡を家柴に舍第させるため、络池や措度との息啡による鼎票甫垫、减瞒甫垫霹を悸卉しているほか、梦弄衡缓涪霹の缓度肠への祷窖败啪を姥端弄に渴めている。
叫疥¨妄甫のホ〖ムペ〖ジより却胯。
Question 2¨
料肋荚である艘填柒黎栏は、附哼、VCAD∈庙∷の甫垫に啡わられておられますが、プレス喇妨シミュレ〖ションに肌いで、この尸填でも告家の度坛と簇わりがあるのですか々
柴家を惟ち惧げた碰介、黎栏は肩扦甫垫镑でしたが、それから1×2钳くらい沸ってからVCADのプロジェクトが幌まりました。VACDは≈菇陇∽とか≈嘿甩∽とか≈萎挛∽など驴呆に畔る湿妄步池附据をモデル步、シミュレ〖ションが乖えるための甫垫で、悸脱步までにはもう警し箕粗がかかると斧ています。
碰家の祸度挝拌は≈ものづくり∽が滦据ですので、VCADの甫垫认跋からみると嘎られた尸填でしかありません。碰家はVCADのものづくりに簇息する尸填にフォ〖カスして5叹の家镑を叫羹させ、倡券のお缄帕いをしています。倡券檬超から簇わっていますので、海稿、VCADが、悸脱步が渴み缓度肠などに何り掐れられていくときには、箭弊に棺弗してくれるものと袋略しています。咐い垂えれば、附哼は、VCADの甫垫倡券抨获弄な檬超といえます。
∈庙∷VCAD¨ボリュ〖ムCAD∈奶疚VCAD∷システムは、ものづくりにおける、肋纷、纷卢、モデリング、シミュレ〖ション、材浑步、裁供などを琵圭することを誊回して、妄甫で倡券しているシステム。
Question 3¨
告家が庙蜗している祸度尸填を澜墒侍にみますと、澜陇ˇ肋纷尸填、板闻尸填、孟刻ˇ松阂尸填の3つに尸けられるようですがˉˉˉ。
もともと碰家の惟ち惧がりがプレス喇妨のシミュレ〖ションからスタ〖トしていますので、そこで禽ったものづくり≈シミュレ〖ション∽に簇する祷窖を动みとして鸥倡しているところです。その面でもこれまでの沸稗から≈ものづくり∽に簇息した澜陇ˇ肋纷尸填が祸度の络染の9充夺くを狸めています。
Question 4¨
澜陇ˇ肋纷尸填のユ〖ザ〖としては极瓢贾メ〖カ〖でしょうか々
 奥疲家墓
奥疲家墓
|
极瓢贾メ〖カ〖というよりも≈极瓢贾缓度∽という山附が赖しいでしょう。ご镜梦の奶り极瓢贾缓度は极瓢贾メ〖カ〖から幌まって、婶墒メ〖カ〖、垛房メ〖カ〖など傀填が弓いです。碰家は≈ものづくり∽に簇わる措度であれば、链て杠狄滦据になります。悸狠、极瓢贾メ〖カ〖のような叼络措度さんから骄度镑が眶叹の踩柒供度弄な措度さんまで、升弓く艰苞をさせていただいています。これまでは极瓢贾缓度の肥丹がよかったこともあり、艰苞翁としては办戎驴いです。 |
Question 5¨
极瓢贾缓度笆嘲にタ〖ゲットとなっている尸填はあるのでしょうか々
排怠、踩排メ〖カ〖などです。これらの缓度では泾挛などを侯っています。ここでもシミュレ〖ションが涩妥になりますので、肩蜗任卿黎が掳する度硷の1つです。
Question 6¨
澜陇ˇ肋纷尸填での泼に卿れ囤の澜墒は部でしょうか々
もともと碰家はプレス喇妨からスタ〖トしていますので、≈ASU/P≥form∽∈庙∷は海までの芜纷で80塑笆惧の任卿悸烙があります。玲く100塑の络骆を茫喇したいと蛔っています。
CADの坤肠はシミュレ〖ション辉眷の100擒くらいの塑眶が卿れるといわれています。ゲ〖ムソフトなどはその1,000擒、あるいは1它擒という辉眷がありますが、シミュレ〖ションˇソフトの辉眷はそれほど络きくありません。眶翁が驴く司めない瓤烫、帽擦はその尸光いのです。ただ、猛苞顶凌はこの坤肠にも碰脸あり、箕と眷圭によっては擦呈が尽砷となる眷圭もあります。
讳どもではプレス喇妨のソフトウエアが办戎の卿れ囤ですが、肌いで践婚喇妨で、构にこれからはナレッジマネジメントなどが卿れていくと斧哈んでいます。
ナレッジ簇息は卿れるまでのリ〖ドタイムが墓いソフトです。シミュレ〖ションˇソフトなどは附眷が涩妥と蛔えば倾ってもらえますが、ナレッジとなりますと、柴家の慌寥みを恃えたり、筛洁步などをやらなければ跟蔡は叫てきませんので、厦が檬」络きくなってなかなか渴まないというのが赖木なところです。しかし、瞥掐した措度をみるとその锐脱滦跟蔡は悟脸としています。
办毋をあげますと、ある措度では、ナレッジとシミュレ〖ションを寥圭わせて艰寥んだ冯蔡、窗喇までの活侯を骄丸12搀帆り手していたものが2搀に负らせたという慌寥み侯りに喇根しました。ものづくりはシミュレ〖ションだけでもダメです。ナレッジも涩妥で、篮刨の光いシミュレ〖ションとナレッジとがうまくかみ圭って喇蔡を刁げた祸毋の1つです。恶挛弄にはデ〖タを委め哈んだり、ナレッジでそのデ〖タを尸老して≈こういうル〖ルがある∽と尸かって、腊妄したりして介めて跟蔡が叫てきます。それを篮刨の紊いシミュレ〖ションˇソフトと寥み圭わせ、悸狠に澜侯しなくても簿鳞弄な坤肠でやれるわけです。この祸毋ではプロジェクトが窗位するまでに5钳を妥しました。
しかし、これによってプレス垛房を澜侯するのに1ヵ奉かかるとしますと、12搀も活侯していたのでは1钳もかかる纷换になってしまいますが、シミュレ〖ションでならあっという粗にできることになります。络升な袋粗没教やコスト猴负に棺弗するので、ユ〖ザ〖さんには润撅に搭ばれました。
海揭べましたように栏缓拉とか跟唯拉は眶檬猖帘できるので、沸蹦荚の数」にナレッジの瞥掐をお传めしますと、すぐに附眷にやれと赌います。しかし、附眷レベルでは、漓扦の么碰荚を弥いてくれるかというとそうではなく、海乖っている度坛に惧捐せでやることになります。筛洁步などは冯菇络恃な侯度ですから附眷の客は幅がることが驴いようです。漓扦をつけていただければもっと橙任できるのですがˉˉˉ。
ところで、讳どもがパッケ〖ジだけで长嘲と尽砷しても砷けてしまいます。长嘲措度は获塑の惮滔も络きいし、パッケ〖ジの眶も坤肠陵缄にやっていますから屈络な眶が叫ています。泣塑のお踩份の≈ものづくり∽というところに、≈ものづくり∽のノウˇハウを蛤えたところで、睛卿をしていくことが涩妥であります。そういった罢蹋で、惧淡の喇根祸毋は祸度橙络する惧で绩憾に少んだ祸毋と千急しています。
∈庙∷ASU/P≥form¨プレス喇妨シミュレ〖ションソフト
妄步池甫垫疥が驴钳にわたる甫垫を奶じて眠姥したノウハウを骏り哈んだ、戮の纳匡を钓さないプレス喇妨シミュレ〖ションソフトウェアで、迫极のプリˇポスト借妄により、庭れたユ〖ザインタ〖フェイスを悸附。房肋纷祷窖荚から附眷澜陇祷窖荚、澜陇么碰荚まで、どなたでも蝗いやすく科しみやすいCAEツ〖ル。
Question 7¨
告家の祸度のメインは、澜陇ˇ肋纷ですが、このほかに、板闻尸填、孟刻ˇ松阂尸填などが非げられていますが。
板闻尸填の澜墒はありますが、まだシミュレ〖ションを蝗うという爬では喇较した辉眷ではないこともあり、塑呈弄な任卿はもう警し
黎になりそうです。
滦救弄に、孟刻ˇ松阂尸填については、≈ASU≥QUICK∽∈庙∷という澜墒を叫しておりまして、≈钝缔孟刻庐鼠∽を梦らせる慌寥みを侯って幢模、给弄怠簇に羌めております。毋えば、丹据模に600骆、链柜の丹据骆へも肌」に羌めており、簇谰孟惰の素どの讳糯称家、叹概舶孟惰のFM庶流渡5渡などに羌墒しています。
∈庙∷ASU≥QUICK¨Alarm System Using early earthQUake warning for Immediate response and Citizens∏safe Keepingの维で钝缔孟刻庐鼠宠脱松阂システム。
弘短俯ベンチャ〖措度庭紊澜墒コンテスト减巨。蜕れの络きさと蜕れ幌めるまでの捅徒箕粗を徒卢ˇ帕茫するシステムで、2008钳1奉、丹据模墓幢より、链柜の扦罢の凋爬について、孟刻瓢徒鼠の钓材を评た。∈钓材妈99规∷
Question 8¨
ところで、黎ほど≈CAD∽という脱胳が叫てきましたが、これ笆嘲にCAM、CAEなどとの般いについて恶挛弄にお兜え布さい。
CADは哭烫を侯るもので、CAMはその哭烫に骄って垛房を裁供したりするもの、シミュレ〖ション∈豺老∷をかけるのがCAEで、碰家はこれをやっています。これらは陵高に息啡していまして、CADがあって、そのデ〖タに答づいて豺老をかけています。 辉眷ではCAD/CAMが络きなウエイトを狸めてはいますが、CAEという尸填もあってCAD/CAM/CAEと弓げていうことがあります。碰家はCADも驴警はやっていますが、肩としてシミュレ〖ションのCAEを面看とした柴家です。
∈庙∷CAD∈Computer Aided Design∷¨コンピュ〖タ毁辩肋纷とも钙ばれ、コンピュ〖タを脱いて肋纷すること。
CAM(Computer Aided Manufacturing)¨コンピュ〖タ毁辩澜陇の维胳で、澜墒の澜陇を乖うためにCADで侯喇された妨觉デ〖タを掐蜗デ〖タとして、裁供脱のNCプログラム侯喇などの栏缓洁洒链忍をコンピュ〖タで乖なうためのシステム
CAE∈Computer Aided Engineering∷¨コンピュ〖タ祷窖を宠脱して澜墒の肋纷、澜陇や供镍肋纷の祸涟浮皮の毁辩を乖うこと、またはそれを乖うツ〖ル。
∈2∷缓≥缓の鼎票倡券が塑呈步
Question 9¨
顶圭陵缄として雇えられるところはどのような措度ですか、そして告家との般いはどのようなところでしょうか々
顶圭陵缄は柜柒ソフトウェアˇメ〖カ〖ではなく长嘲ソフトウェアˇメ〖カ〖です。泣塑のシミュレ〖ションの答撩祷窖は络池も妄甫もレベルは光いのですが、苹恶となって坤の面に叫搀っているものは长嘲澜墒が驴いのです。长嘲は柜の蜡忽として润撅に缄更く瘦割されたり、络池や甫垫怠簇などと措度との乖き丸も宠券で、ベンチャ〖篮坷も并拦ですからいろいろな柴家が伴っています。
办数、柜柒は荒前ながら络池霹の改」の甫垫レベルは光いのですが、长嘲のように艰り寥みがなされてこなかったので、悸脱澜墒が警ないのが悸攫です。骄って、ものづくりシミュレ〖ションˇソフトウエアの坤肠では、长嘲澜墒が络染で、柜柒にはせいぜい碰家と1、2家しかありません。
メインの顶圭陵缄である长嘲澜墒と碰家との般いは、改」の澜墒によって佰なりますが、まずフレンドリ〖といいますか、≈嶷いところに缄が葡く∽というようなソフトを誊回している爬が泼魔だと蛔われます。また、誊回す数羹拉も络きな般いがあります。拒嘿はいえませんが、长嘲のパッケ〖ジソフトはシミュレ〖ションだけであるのに滦して、碰家は光烧裁擦猛で、ものづくりを琵圭弄にサポ〖トするような澜墒ˇサ〖ビスの捏丁を誊回しています。つまりは、シミュレ〖ションだけでは啼玛豺疯にはならないのです。シミュレ〖ションからは≈こういう掘凤ならこういう冯蔡になる∽ということまでは尸かりますが、稍恶圭が叫た箕にどうするかという豺は叫てきません。≈どうするんだ∽∈Solution∷というノウˇハウを裁えてやっていきたいと雇えています。
黎ほど、ナレッジとシミュレ〖ションの喇根祸毋でもお厦しましたように、≈ナレッジ∽との寥み圭わせによって、办檬と汗侍步できると雇えています。碰家澜墒≈ナレッジマネジメントシステム∈ASU/TK-base∷∽∈庙∷があり、それの苹恶となりえます。
ちなみに、艘填柒黎栏がよく赌ることに、ITS∈Information Technology on Science∷があります。これはものづくりにはScience に答づいたITが脚妥であり、碰家はITS祸度を鸥倡している措度というのも泼咖の1つです。
∈庙∷ASU/TK-base¨ナレッジマネジメントシステム、ものづくり尸填における梦急攫鼠の琵圭マネジメントシステム
∈弘短俯ベンチャ〖措度庭紊澜墒コンテスト减巨。∷
Question 10¨
告家が脚浑している≈ものづくり∽という爬では、メインユ〖ザ〖である澜陇度は柜柒から长嘲に渴叫しています。これによって≈缓度の鄂贫步∽といった啼玛が底しくいわれていますが、告家はこのような缓度菇陇の恃步の逼读を减けているのでしょうか々
その滦炳忽として、长嘲渴叫をお雇えでしょうか々
长嘲に渴叫しているところは、祷窖というよりもむしろコストだけで尽砷をしなければならないところが面看ではないでしょうか。光い祷窖蜗を积っているところや润撅に烧裁擦猛の光いものを侯ろうとするところは柜柒でやらざるを评ないし、そのときにITがどうしても涩妥となりますから、碰家としては柜柒メ〖カ〖の长嘲渴叫についてはあまり看芹してはおりません。悸狠、メ〖カ〖が柜柒に荒って乖っている尸填は烧裁擦猛の光いところを晾っています。それだけに、どうしてもITを完りつつやらざるを评ないので、看芹はしていません。
Question 11¨
箭弊菇陇について磺いたいのですがˇˇˇ
任卿黎は、黎ほど拷し惧げましたように、澜陇ˇ肋纷尸填が9充を狸めております。办数、卿惧菇喇は、システム倡券の减瞒が6充、パッケ〖ジの任卿と瘦奸瘟を崔めて4充となっています。绕脱パッケ〖ジを任卿していますと、≈こういうことはできないか∽などユ〖ザ〖さんからのカスタマイズ步の妥司が叫てきますので、システム倡券の减瞒が冯菇驴いです。このほかには、柜踩プロジェクトなども减庙しています。
Question 12¨
祸度を费鲁券鸥していくために涩妥な庭建な客亨の澄瘦のための滦忽や伴喇忽、附哼の骄度镑眶などお使かせ布さい。
≈妄甫ブランド∽を恢羹した客亨が、极脸に礁まってきますので、客亨澄瘦の烫ではそれほど鹅汐はありませんが、ややもすると≈甫垫荚としてのマインド∽が动いので、≈措度客に伴てていくこと∽が络磊な草玛で、ビジネス甫饯などをやらせています。附哼家镑ˇパ〖トを崔めまして50叹ほどの 骄度镑がおりますが、そのうち祷窖簇犯が30叹、蹦度么碰が6叹、そして荒りが祸坛簇犯ˇ输锦镑やパ〖トです。
Question 13¨
蹦度么碰6叹は警ないような磅据を减けますが、どのような蹦度宠瓢を乖っているのでしょうか々
蹦度については咖」なスタイルがあって、硷梧にもよりますが、パッケ〖ジ任卿は洛妄殴沸统でおこなっています。また减瞒倡券祸度などはエンドユ〖ザ〖に木儡叫羹いていき、慌屯を低めてシステム倡券をしたりしております。减庙から羌墒までのリ〖ドタイムは墓いものですと染钳、柜のプロジェクトですと1钳を妥するものもあります。
Question 14¨
海稿ともこのようなビジネスモデルで祸度鸥倡を渴めていかれるのでしょうか々
お狄さんから≈草玛を办斤に豺疯したい∽、≈鼎票倡券弄にやらせて瓦しい∽というニ〖ズが呵夺笼えています。シンプルなシステム倡券であればお狄屯の妥司をそのまま磺えばできますが、糠しい祷窖を倡券するには悸赋が涩妥になります。碰家にはそのような悸赋刘弥がありませんので、碰家がシミュレ〖ションをやって、お狄さんに悸赋をやっていただいてくという舔充尸么を汤澄にした鼎票倡券が笼えています。海稿はこの祸度を凯ばしていきたいと雇えています。
Question 15¨
鼎票倡券の面で券栏する糠たな祷窖は≈泼钓∽を艰评していくのですか々
糠しい祷窖の眷圭、鼎票叫搓荚の办家に裁わることになります。ライセンスˇフィ〖をいただくというところまではまだ魂っておりませんが、海稿鼎票倡券の面で糠しい捌凤が笼える材墙拉があります。
∈3∷糠5ヵ钳沸蹦纷茶がスタ〖ト
Question 16¨
沸蹦纷茶についてお使かせ布さい。
笆涟、ホ〖ムペ〖ジに沸蹦纷茶を很せていましたが、これは附哼斧木し面です。讳が家墓に舰扦した狠に09钳3奉袋を妈1袋とする糠たな5ヵ钳沸蹦纷茶の忽年に缅缄しまして、1钳くらいかけて艰寥んできました。5钳稿の誊筛として、卿惧光10帛边、沸撅网弊2帛边、そして庚升ったいようですが、≈CAE尸填で泣塑办のブランドを侯ろう∽と腽っております。柒推としてはフラットな寥骏への斧木し、笺缄の却脓など、ガラッと恃えていこうと、海钳の5奉に家柒に给山しました。ロ〖ドマップを侯る檬超まで渴んできましたが、サブプライム啼玛の券栏、极瓢贾缓度の皖ち哈みなどの茨董の恃步もありましたので、家柒の附斗を尸老し、柒婶のプロセス、任卿、衡坛、寥骏、喀坛涪嘎などを浩刨斧木して、この2、3ヵ奉で猖柠惹の忽年に掐っております。この沸蹦纷茶はサマライズしたものをホ〖ムペ〖ジに夺泣アップする徒年です。
Question 17¨
沸蹦纷茶の恶挛弄な数忽についてはˉˉˉ。
≈寥骏恃构、笺缄却脓、ナレッジ、シミュレ〖ション、ノウˇハウを突圭した澜墒倡券∽などと庚では词帽に咐っておりますが、蹦度のマ〖ケッティングをどう动步するか、称澜墒の动步、祷窖里维など另圭弄に艰寥んでいって坤の面にないものを叫して卿惧を凯ばしていかなければなりません。海稿5钳粗のそれぞれの钳に部をやるかの纷茶を惟ててじっくり艰寥んでまいります。咐い垂えれば、≈孟蜗をつけていこう∽というイメ〖ジで雇えております。5钳稿にはVCADも甫垫の檬超から悸脱步に掐ってくると蛔っています。そうなれば睛卿のチャンスも叫てくるでしょう。
これからは帽なるソフト舶であっては顶圭戮家に砷けてしまいますので、ものづくりに端蜗夺いところを晾っていきます。この5钳纷茶のPlan、Do、Check、Actionをキチンとやることが脚妥で、海までの萎れを慷り手ってみますと碰家はどこが煎いか、部がまずいのか、どう动步するかも斧えてきています。
警しずつ恃わってきていると蛔いますのは、黎ほども拷し惧げましたように、≈办斤にやろう∽というところが笼えてきていますし、それも陵碰络缄措度が叫てきていますので、その措度で倡券したプログラムをその措度との鼎票ブランドで任卿させてもらうという拷懒をしているところです。こういう喇根祸毋をたくさん笼やしていきたいと蛔っています。
Question 18¨
IPOについてはいかがでしょうか々
5钳で卿惧10帛边、沸撅网弊2帛边をやっていければ臭及の惧眷が斧えてくるのではないかと雇えております。肋惟碰介は、廓いで≈玲袋にIPO∽と咐ってきましたが、2钳涟に、笺闯の乐机も纷惧したため变袋となりました。浩刨、墓いレンジで雇え、5钳の沸蹦纷茶をベ〖スにIPOに羹けてスタ〖トしたいと雇えています。ただ、そう蛔っていた甜黎にサブプライム聋瓢などで肥丹がぐっと碍くなり、しかも极瓢贾缓度が络きな虑封を减けるなど、ここ1钳途りは阜しい觉斗が鲁くでしょうが、墓い誊でみれば、泣塑の极瓢贾は长嘲の极瓢贾メ〖カ〖と孺べて、端めて浅锐の紊い贾を侯ることができるので、碰家への逼读はあまり看芹はないのではないかとみております。
Question 19¨
呵稿に、告家との定蜗簇犯にある柴家にはどのようなところがありますか々
| 笆涟のホ〖ムペ〖ジでは圭驶の纷茶もありましたが、咖」なことがありまして栖好しました。圭驶することで祸度の升は弓がりますが、祸度尸填が络きく般っており、惦涂挛废その戮の掘凤も般いましたので圭罢に魂りませんでした。しかし动い定蜗簇犯は苞鲁き冯んでいます。その嘲の定蜗簇犯では、妄甫ベンチャ〖のうちバイオ废措度とはあまりシナジ〖跟蔡は斧哈めませんが、供池废では碰家と击たような尸填をやっているところがありますので定度簇犯が菇蜜できます。呵夺の祸毋では、极瓢贾メ〖カ〖から慨完を评ている甫猴祸度をやっている措度さんとのコラボも幌めました。 |
 下各インキュベ〖ションプラザ |
また、碰家が掐っています下各インキュベ〖ションˇプラザの掐碉荚は妄甫ベンチャ〖だけではありませんので、碰家の柴墓が慌齿けて、掐碉している戮のベンチャ〖措度との蛤萎柴を冯喇しまして、髓奉お高いの寿动柴をやったりして陵高のビジネスチャンスを弓げております。
诞脚なお厦を铜岂うございました。